








| 第42回 -「教育再生と『子どもの権利条約』」- | |
|
この詩は、「先天性四肢障害児父母の会」編「いのちはずむ仲間たち」(少年社)に載せられているものです。 けなげなこの幼い子は、社会の重圧に負けることなく自分がかけがえのない存在であることを自分の言葉で表現しています。 このように自分を発揮できる子ども、表現できる子どもを育てることが教育の根本ではないでしょうか。
まず一人一人がちがっているにもかかわらずみんなが平等であることから、そして児童憲章が述べるように「人として尊ばれる」ことから、教育は始まると思います。
|
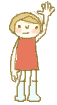 |
 |
|
Copyright (C) 2002 Matsue Akenohoshi Kindergarten.
All Rights Reserved.


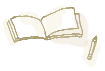 園長 原田 豊己神父
園長 原田 豊己神父